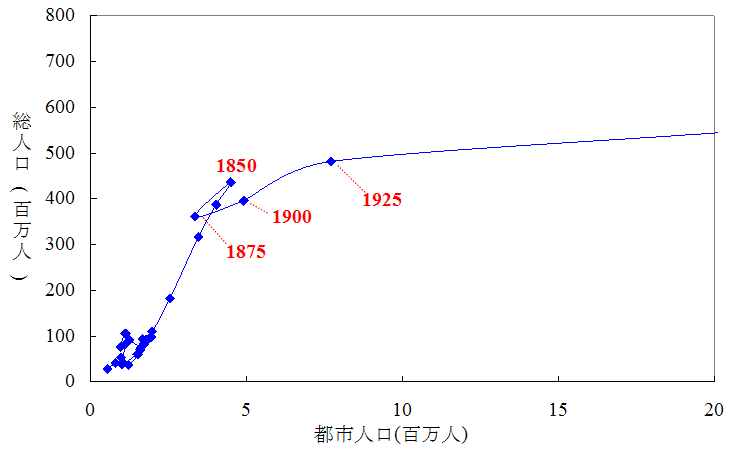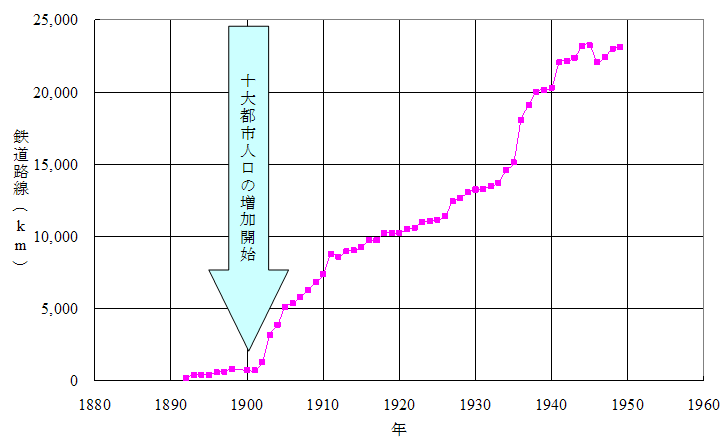|
第五章 考察 (続き)
3. 境界年以降の都市人口構造の変化について
境界年を境に、十大都市人口と総人口の関係が変化したが、この変化をもたらしたのはどのような社会変動であったのだろうか。中国における1900年前後の都市人口と総人口の動向を細かく観察すると(図 V-8)、1850年から1875年にかけて総人口、都市人口が共に減少した後、1925年まで最初の勾配低下、1925年以降さらなる勾配低下が起こっている。つまり1900年を中心とした前後25年間に総人口の増加に対する都市人口の増加の速度が高まっていることがわかった。
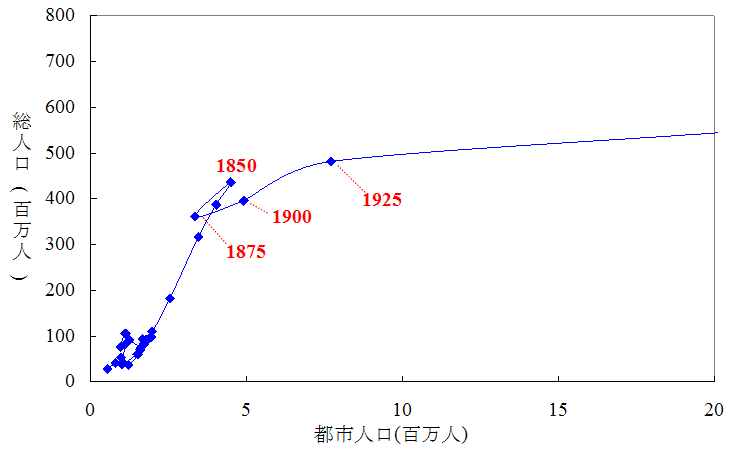
図 V-8 十大都市人口と総人口の動向(中国: 1900年前後)
1875年の総人口、都市人口の減少は、1864年に終結した太平天国の乱、および1872年まで続いた回族の反乱によるものと考えられる。その後1925年までのの中国では、1912年の中華民国成立、1921年の中国共産党成立と大きな社会変化があった。それは清朝から民国という政治的な変化、都市インフラの整備による都市が収容できる人口の増加、産業構造の変化による第二次、第三次産業の拡大の結果としての都市人口の増加、移動のための交通手段の発達、といった要因が考えられる。
中国の人口移動は、民国以前の清朝体制化でも国外、国内の人口移動が多くあったことが知られている。清朝前期から後期にかけて四川、広州、台湾、遼東等に向けての人口移動が、また清朝後期にはアヘン戦争後の苦力、つまり単純労働者の国外移民の増加、太平天国の乱による国内人口移動があった(葛1997、曹2001)。また清代には保甲制度として機能していた戸籍制度についても、それは民衆の自由を束縛するものではあるが、実際には大規模な人口移動は起こっており、それに対応するために「原籍主義」ではなく「原住地主義」とすること、移動民に対する保甲制度の法令が発せられるなど人口移動を前提にした制度となっていた(王威海2006)。しかも道光(1821年)以降は清政府の弱体化により保甲制度の崩壊が進行し、人口移動に対する規制はさらに少なくなったとされる。したがって1912年に清朝から民国に政治体制が変わったからといって、それまで抑えられていた人口移動が急に活発化した、という訳ではないように思われる。
都市インフラの整備としては、例えばそれまで都市の拡大を物理的に阻害していた城壁の撤去などを挙げることができるが、これは都市人口増加の原因というよりは結果というべきものであろう。また1925年前後の都市インフラとしては、電気が都市の重要なインフラにはまだなっておらず、上下水道が都市の人口許容力を規定する可能性もあるが、この上下水道が1925年を境にして大きく変化したかどうかは明らかでない。
都市人口増大の要因として、交通手段の変化に注目すると、1900年は鉄道の開発が始まったときであった。中国においては1876年上海-呉淞間14.5kmにイギリス商社が敷設したのが最初の鉄道であるが、その後清朝時代の1911年まで大きく線路が延長し、その後1925年までにゆるやかな上昇を示している(図 V-9)。これは1900年前後の都市人口の増加に時期を同じくしている。中国では1750年から1900年にかけて都市人口に比べ総人口が大きく上昇したが、これはプロト工業化により農村で人口が膨張し、それが1900年以降の鉄道建設により一気に都市部へ流入したと解釈することができる。
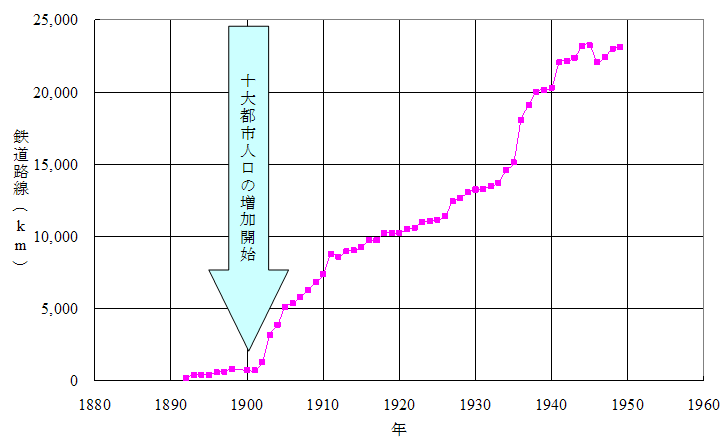
図 V-9 中国における鉄道路線(km)の延長動向
出典 : 1898年まではMitchell(1998)、1900年以降は郝(2000)による。
この鉄道開発と十大都市人口の相対的増加について各国で観察すると、日本、フランス、ドイツにおいても、本格的に鉄道交通が開始した時期と都市人口増大の時期は一致している。
都市人口の増加は高い出生率ではなく高い移入率により起こっていたことを考慮すると、鉄道が都市と農村を結んだことの意義は大きい。現在であれば鉄道でなければ、車、飛行機があるが、鉄道が登場する前の人々の移動手段は、水上交通としては船が、陸上交通としては馬があったが、基本的には徒歩である。距離においても人数においても移動の程度は限られたものであった。鉄道の開発により農村から都市への人口集中が加速度的に起こり、交流圏の拡大が起こったと考えられ、その拡大の変化の度合いは過去1900年間には見られないほどの大きな変化であったと考えられよう。蒸気機関の発明と応用が産業革命の主要な技術革新であるならば、鉄道はその結果といえるが、鉄道開発により大規模な人口移動が可能となって都市人口が増大し、その結果工業化が進展したのであれば、鉄道は産業革命の原因でもあったということになる。
しかし、この鉄道開発の影響は、すべての国・地域にあてはまっているわけではない。例えばイギリス、アメリカ合衆国、インドでは、鉄道開発の始まりが都市人口増加と連動していない。鉄道が最初に敷設された英国、新大陸のアメリカ合衆国では、都市人口と総人口の関係自体に明瞭な境界年が見られない。同じく新大陸のアルゼンチンでは、鉄道建設により海外からの移民による大幅な植民が進み、総人口が増えたとされている(今井1985)。鉄道建設により既存の農村人口をとりこんで都市人口が増えたというよりは、総人口そのものが鉄道建設により増加したような新大陸では、都市化自体が異なったメカニズムによりもたらされているのかもしれない。インドの場合は、イギリス植民地政策により、早くは1853年から鉄道建設が始まっているが、総人口、十大都市人口は共に、大きな増加が始まったのは1931年であり、総人口と十大都市人口の相関変化も1931年を境界年としている。中国の場合は1900年の境界年以前に大幅な総人口の増加があり、それが鉄道建設の開始と共に一挙に都市に流れたが、鉄道があっても総人口自体があまり増加していなかったインドでは都市化が鉄道の普及により促されなかった、と考えることも出来る。すなわち、鉄道建設が境界年の都市化の進展をもたらす必要条件は、十分な農村の剰余人口がある場合である、ということである。
都市人口と総人口の相関変化は、移動手段の変化だけではなく、工業化の進展による産業構造の変化といった、都市の受け入れ側の事情を含めた複合的なプロセスによるものであり、さらに詳細な分析が必要であるが、本モデルで用いた、1850年、1900年という都市化に関する境界年をもたらした要因は、人の動きを加速させた鉄道開発が重要なものであると指摘できよう。
前へ / 次へ
TOP
|