訳者あとがき
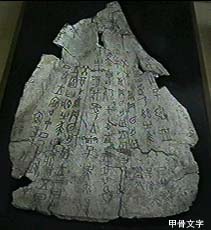 中国河南省安陽県で甲骨文字が発見されたのは、今から約100年前の1899年の事だ。漢方薬局で、マラリアの薬として売られていた「龍骨」に文字が書いているのを発見したのは、清の大学長、王(イ)栄であった、とされている。
中国河南省安陽県で甲骨文字が発見されたのは、今から約100年前の1899年の事だ。漢方薬局で、マラリアの薬として売られていた「龍骨」に文字が書いているのを発見したのは、清の大学長、王(イ)栄であった、とされている。
中国古代文字研究は、この甲骨文字発見までは、金文と呼ばれる青銅器に刻まれた古代文字を対象としていただけであったのだ。甲骨文字の研究は、やっと始まったばかりなのである。
いうまでもなく漢字は、現存する文字の中で唯一象形文字であるといわれる。その生い立ちは、「説文」から始まって、様々な解説が試みられてきた。しかし定説はあっても証明するものはない。
中国の歴史自体も、近年の発掘調査で新事実が次々と明らかになってきている。逆に言えば、わかってないことはまだまだ沢山あるのである。
人類は、遡るとたった一人の女性から生まれたことになる、という「ミトコンドリア・イブ」仮説が生まれたのは、1987年、今からたった10年前である。
 ミトコンドリアは、細胞の中にある、エネルギーを造る器官だが、それ自体の中にDNAを持つ。通常言われているDNAは、細胞の核にあるDNAなので、それとミトンコドリアのDNAが持つ情報は、全く別物だ。
ミトコンドリアは、細胞の中にある、エネルギーを造る器官だが、それ自体の中にDNAを持つ。通常言われているDNAは、細胞の核にあるDNAなので、それとミトンコドリアのDNAが持つ情報は、全く別物だ。
卵子と精子の核のDNAは、受精の時にミックスしてしまうが、受精の際に卵の中に入っていくのは、精子の核などほんの一部分である。つまり、精子のミトコンドリアは、受精卵の中に入っていかない。そうすると、新しい命=最初の細胞にあるミトコンドリアは、卵子、つまり母の体にあったミトコンドリアであり、その中のDNAは、母の体内にあったミトコンドリアDNAをそのまま受け継いだもの、ということになる。
アメリカの分子生物学者レベッカ・キャン博士が、世界百数十民族の妊産婦から胎盤を譲り受け、ミトコンドリアDNAを分析すると、それらすべてが同一起源にたどりつくと結論づけた。突然変異のスピードから、最初のその「ミトコンドリア・イブ」は、今から29万年から14万年前にアフリカに住んでいただろう、とされた。
ミトコンドリア・イブは、家族と、友達と、おしゃべりしていただろうか? まだ文字は持っていなかっただろう。けれども、その子孫が世界中に散らばっていって、母親と同じことばをしゃべりつづけたのではないだろうか? ミトコンドリア・イブという一人の人間が今の全ての人類の起源であるとすると、言葉ももとは一つだった、ということになるのだろうか。
話し言葉を記述し始めたのは、それよりずっと後のことらしい。それでも現存する世界の書き言葉は、遡っていくと漢字とアラム語に行き着くといわれる。
旧約聖書が書かれた言葉はヘブライ語といわれているが、その古代ヘブライ語も、その時その地域で使われていた文字体系のうちの一つにすぎない。その文字体系をアラム語と呼ぶ人もいるし、フェニキア語と呼ぶ人もあろう。

シリア・ダマスカス博物館に、世界最古のアルファベットが鎮座している。それは、シリア西北部のラスシャムラ(ウガリット)の古代都市遺跡から発見された、指一本ほどの粘土板に記されている。楔形文字に似た30程の文字は、左から右に、一字ずつ示されている。文字を習う子どもの教科書(板?)として用いられたのだろうか?
これが、世界最古のアルファベットと呼ばれるのは、その文字が一つずつ、アラプ、ベータ、ガマル・・・といった発音を表しているからである。その発音順序は、アラム文字を経て、現在のアルファベットやキリル文字、アラブ文字やインド諸言語に引き継がれていった。
それでは漢字はどうか? 漢字は象形文字のまま残り、その文字の多さ、複雑さからも、アルファベット発明前のヒエログリフや楔型文字と同列に並ぶものと考えられる。とすると、漢字はそこから発達したのだろうか?


中国の著名な歴史家、郭抹若は、漢字の起源は楔形文字にある、という説を支持していたようだ。また、散発的にアラム語と漢字の類似がみられることもある。例えば、世という漢字は、シー(shi)と読むが、それと、アラム語、もしくはヘブライ語のアルファベットのシーンは、何とも似ているのである。
創世記に書かれている洪水伝説や、最初の人間の話は、旧約聖書だけに書かれているわけではない。世界各国に、類似した話が伝わっている。旧約聖書は、古代世界に残された口承説話を文字にして残した、という意味で重要なのである。旧約聖書はユダヤ・キリスト両教の聖典ではあるが、古代説話の歴史的資料として考える方が、我々日本人にはなじみやすい。この世界最古の歴史書も、最近の死海文書の発見とその研究によって、見直しが検討されている。
それにしても、なぜ漢字と聖書の関係を説くこの本に興味を引かれたのだろうか? 中近東、オリエントという遠い文明が、われわれがいる東アジアにぐっと引き寄せられる様に感じるからであろうか?
人類文明同一起源説というのは、いつの時代にも存在した考え方である。私も世界各地を旅行して、人類はどうも結局は同じである、という感触を持たずにはいられない。
食べて寝て、楽しんで働いて、生まれて死んでいく。それぞれの文化や生活環境により、各人が本来持つ能力が生かされたり埋もれたりするけれども、その能力は、どの国でも、どの人口集団でも同じように分布している。昔も今も、それは根元的なところで同じなのだ。
野蛮で、粗野で、土地に縛られ世界観が狭い人々・・・といった、古代人に対する固定概念は捨てるべきである。地球は狭い。毎日時速4キロで8時間歩き続けたら、3年と6ヶ月で地球一周、4万キロメートル走破である。そして、知的好奇心は昔から存在した。他の優れた文明に触れたいという思いは、古代人であっても強かったに違いない。
今、少なくとも地球上では、世界が狭くなった。飛行機でどこにでも行け、人工衛星で世界のすみずみまで見渡すことができる現代には、もはや夢見るだけの「異国」は存在しない。これまで別々に分化してきた人間文明を、もう一度整理し直して統合しようと思うのは、自然な人間の感覚であろう。
中国文明は、その古い歴史にも関わらず、どうも孤立して考えられがちである。けれども、モンゴル人は中国に国も建てたし、ヨーロッパも征服した。大地を駆け抜けようという意志さえあれば、ユーラシア横断など至極簡単であったろう。シルクロード遺跡の発掘調査も進んでいるし、中国イスラム教徒の歴史も古い。中国研究は、漢字の習得が必要であったから、漢字圏以外の人々には敷居が高かったろう。そのため、世界の古代史研究の中で、中国だけ別物として疎外されていたきらいがある。またここ50年間の中国情勢は、世界に開かれた中国古代研究を行うには、ちょっと不都合な時代であったことは確かである。しかし中国と、中央アジアを経由したオリエントとの関係は、思ったよりも近く、これから発掘されるべき新事実は山のようにあるだろう。
日本からヨーロッパに飛行機で飛び立つと、降りた時の文化は全く「異質」に思えるが、飛び越えた、その下に綿々とつながった国々は、少しずつ変化しながら連続しているのだ。民族、国家とほんの最近の都合を云々するよりも、世界人類みな兄弟(姉妹)である。この本が、そうした意識を覚醒させる、清涼剤になればいいと思っている。
戻る
Copyright 1997- (株)リンツ
 ミトコンドリアは、細胞の中にある、エネルギーを造る器官だが、それ自体の中にDNAを持つ。通常言われているDNAは、細胞の核にあるDNAなので、それとミトンコドリアのDNAが持つ情報は、全く別物だ。
ミトコンドリアは、細胞の中にある、エネルギーを造る器官だが、それ自体の中にDNAを持つ。通常言われているDNAは、細胞の核にあるDNAなので、それとミトンコドリアのDNAが持つ情報は、全く別物だ。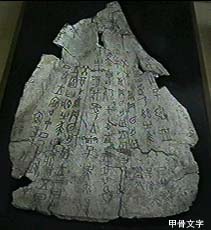 中国河南省安陽県で甲骨文字が発見されたのは、今から約100年前の1899年の事だ。漢方薬局で、マラリアの薬として売られていた「龍骨」に文字が書いているのを発見したのは、清の大学長、王(イ)栄であった、とされている。
中国河南省安陽県で甲骨文字が発見されたのは、今から約100年前の1899年の事だ。漢方薬局で、マラリアの薬として売られていた「龍骨」に文字が書いているのを発見したのは、清の大学長、王(イ)栄であった、とされている。

